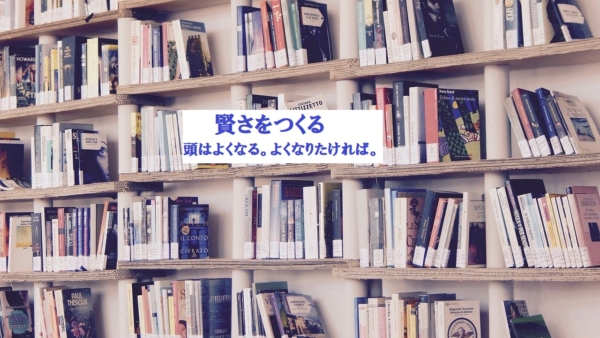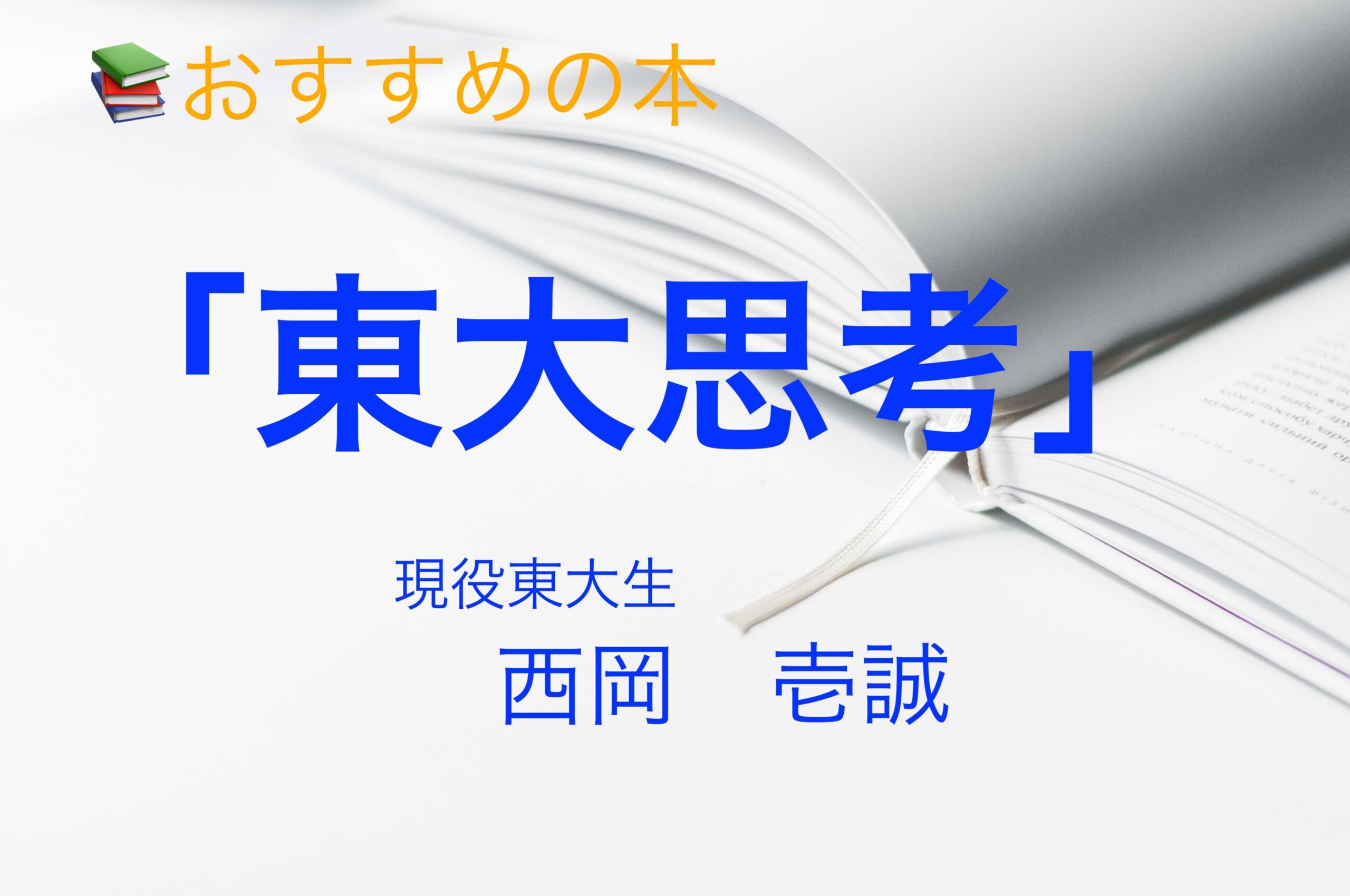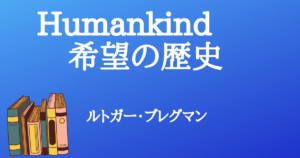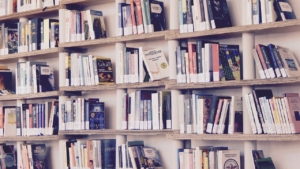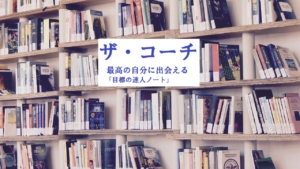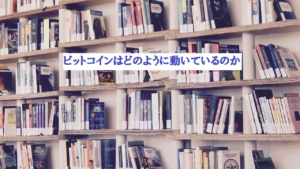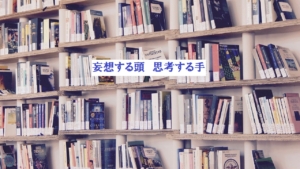お子さんから
「こんなことを勉強して、役に立つことあるの?」
「おかあさん、二次関数とか、古典とか、『生活の役にたってるわ~』って思うことある?」
なんて聞かれたことはありませんか。
わたしは、子ども3人×100回以上は聞かれました。
ぶっちゃけ、わたし自身もそう思っていました。
でも、大人になってみると、二次関数とか、古典とか、知らなくてもいいかもしれないけど、知ってて損はないし、知識って、たくさんある方が、考えがふくらんでおもしろい。
断片的な考えはあるものの、「これ」という答えはないまま過ごしてきました。
この本のおかげで、何十年もモヤモヤしたものが、すっきりと晴れました。
わたしの答えが出たのです。

子どもの頃にインプットした多くのことを、自分の頭で考え、理解し、大人になって上手にアウトプットできる人が『賢い』人。
だから、小学校低学年ではインプットできたかどうかを計る単純なテスト問題が多く、学年が上がるにつれて説明をしたり、自分の思考力が問われる質問が出てくる。
思考力を鍛えるには、まずいろんな分野の知識を得ることが必要なのです。
この本を読んで、過去何百回と聞かれてきたけど、きちんと答えられなかった問いの答えを出すことができました。
本を読み終えたときに、二男がいたので、「答えが出たぞ~~」と↑の発言をしました。
「お母さん、すげ~!! 論破や。」
二男からこんな言葉が出て、思わずガッツポーズ✊
ふだん、屁理屈こねて対抗してくる二男が、あっさりと私の考えを受け入れました。
最近、毎日のように、「勉強する意味が分からんわ~」って言っていたのに。
彼もすぐにこの本を読み始めました。
本書の中では、『賢さ』は、『具体』と『抽象』の往復運動である、といっています。
わたしが、自分が幼いころや、子どもたちからの疑問、「こんなことを勉強して、役に立つことあるの?」に対して、
「大人になってみると、二次関数とか、古典とか、知らなくてもいいかもしれないけど、知ってて損はないし、知識って、たくさんある方が、考えがふくらんでおもしろいし…。」
という、断片的な考えは、『具体』だったのだ、ということが分かりました。
わたしには『抽象化』が足りなかったのです。
この本では、抽象化の能力はインプット力だといっています。
ということは、わたしはインプットが足りていない。
もっと、インプットして、インプットしたものを自分の頭で整理し、『抽象化』する力をつけていこう!
これからの目標もつくることができた1冊でした。